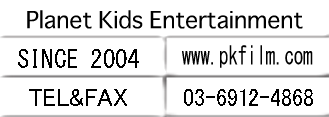
闇の旋律 |
 |
 |
 |
|
監督/伊藤秀隆 脚本/伊藤秀隆 千葉大樹 川渕武士 プロデューサー/伊藤秀隆 深澤耕介 今井友也 撮影/柳 宗祐、伊藤秀隆 キャスティング/坂本マリ 音楽/奥野勝利 企業からの出資を受けてPKが製作する初の作品。「インターネットは一人でやる事が多いからホラーなどで怖がらせるのに打って付け!」という伊藤の企画に「関西マルチメディア」と言うプロバイダーが賛同したことから始まった企画である。 ※当時掲載された関連記事 1、日刊サン(LA) 2、Bridge U.S.A. また、この作品でプロデューサーに抜擢された深澤耕介は、渡米してから半年しかたっていない当時19歳。彼の奮闘記を是非読んでください。 |
| September
15, 2002 02闇の旋律 初めてのプロデューサー戦記1 プリプロ編
そもそも、この製作に参加したきっかけは、LA留学のバイブルにもなっている放送作家の鈴木さんのホームページでの「クルー募集」の書き込みであった。この鈴木さんの「インターネット的エンターテイメント屋の日々」、監督の親友で現在スタジオ ジブリで働いている西さんの「Nitch.Net」、そして我らが「Planet Kids Entertainment」、はテンターテイメント業を目指す人にはオススメ。 LAに来て約7ヶ月、何も映画製作をしていない自分に焦りを感じていたこともあり、その伊藤監督の書き込みを見て直ぐ、「何か手伝わせてください。僕はプロデューサー志望です。」とメールを出しました。そもそも、Planet Kidsは出来上がった作品をどうするかという制作後にも力を入れている気がしていた為、僕にとって学べるものが多い気がしていた。しかも、関西の大手プロバイダー関西マルチメディア(通称:ZAQ)がスポンサーだ。これはやらないわけにはいかなかった。 伊藤監督と数回会って、しばらく経った頃にMSNメッセンジャーで呼びかけられ、 さて、引き受けたものの、僕は実際何をやったらいいんだろう?と、今思えば引き受けた自分が恐ろしい程のドドド素人だった。そこで、Little
監督、トモ、俺の3人でのミーティングが始まったのもこの頃だった。まず、スタッフを探し、予算を算出し、その割り当てをするなどが話しの中心であったと思う。プロデューサーという名前に浮かれていた僕はここで、現実的な問題に当たった。まずはPropである。僕はこれが小道具だということを知らなかった。そのように、映画を製作するにあたって、どういった人が必要なのか?どんな物が必要なのか?ほとんど知らなかったのだ。このミーティングを経て、何となくLocation
September 16, 2002
1. 監督ヒデさんが責任者だと思わず、自分がそれだと思う。 この2つであった。1は要するに、責任を持って取り組もうということだ。撮影が出来ない、撮影が遅れるといったことは自分の責任であると思い込んだ。2は、あるプロデューサーがいった言葉だった。「誰かが起きている時は絶対に眠そうにはしない。そうすると、この人はいつ寝ているのだろうとみんなが思い、この人はすごいと勘違いする。」と。プロデューサーは、こいつには絶対かなわないというものを持っていなくてはならないとも言っていた、経験の無い僕にはそれしかないとその時思った。 さて、引き受けたものの何の機材が必要なのか分からなかった。大体必要なものは聞いていたが、具体的に、例えば、HMIライトとはどんなライトか知らなかったため、どう探したらよいのか見当もつかなかった。しかも、機材費に割り当てられた予算は決して多くは無かった。というより、コネを活かしてタダで借りようがテーマであった。機材のリストは、忙しいトモに迷惑を承知で頼み作ってもらった。これで、後は交渉だ。いかに安く借りられるか、なぜか妙に楽しかった。 こうしている間もミーティングを重ね、企画も進んでいた。3作の内、一作はヒデさんが一人で書き、1つはPKの脚本家である ダイキさんがヒデさんと共同で執筆し、最後の一つはヒデさんが加わらず、別の人に頼むことになった。これは、ヒデさんの「演出だけに専念するということもやってみたい」という事からだった。 この頃ファイナルの試験が控えており、かなり厳しいスケジュールであったが、要領良くやらないと、多くのことを動かすプロデューサーとして働けないだろうと思った。 機材を借りるにあたっては、LA411というロサンゼルスの映画製作に必要であろう会社の連絡帳があり、WEBサイトで検索も出来き、かなり使える。LA411を使い、まず必要なレンタル会社をリストアップし、はじから連絡をしてみた。必要な機材は分かっている。後は交渉していかに安く借りられるかが問題であった。撮影は夏休みで、2週間一気に撮影が出来るため、割引がききレンタル料もやすくなる。ヒデさんの通うUSCの肩書きはかなり使えたが、それだけではまだ高い。ここからが重要であった。映画製作がとても盛んであり、学生映画に協力的なハリウッドにいるのだから、中途半端にプロっぽく気取らず協力してくれと頼む感じで交渉した。後は、何度も電話をし、覚えてもらい、少しずつ値段を下げていってもらった。特に高かったのは、発電機だった。一作目「BOX」のスピンシーンを夜撮るには、どうしても必要だった。 また、機材を借りるにあたってのもう一つの大きな出費は、保険代であった。保険に加入が絶対条件だと知らなかった僕は、計算外の出費にまた頭を悩まされた。最低入らなくてはいけないのが、General
September 17, 2002
ファイナル試験も終わり、完全映画モードになったのは、5月の半ばだった。撮影開始まで、2週間ほど。スタッフも完全に足りておらず、撮影が出来るのか真剣に危うかった。しかし、トモが大体のスタッフは集めていたので、あとはインターネットの掲示板への募集の書き込みに期待した。留学生が多く集まるサイト、すなわち前述のインターネット的エンターテイメント屋の日々、びびなび、映画留学生が訪れるPKサイトに書き込んだ。これでやっと、ほぼ必要な人数が集まった。留学生はかなりびびなびを見ているようだ。 機材のレンタル先はまだ完全に決まってはなかった。少しでも安いところがあれば、そちらにしたかったからだ。あちらにとって僕は、さんざんな客であったかもしれない。機材についての知識がほぼ無かったため、インターネットで調べたりはしたが、中にはレンタル会社の人に「それは、何?」などと聞いていた。とにかく、撮影が出来なくなるということを避けるために、予約のようなかたちでキープだけはしておいて貰った。忘れられないように、こまめに連絡はしたが。 撮影まで1週間をきったころ、脚本の変更に伴った、ロケーション変更の電話があった。実は、これまでほとんどロケ先を見つけられないままであった。その変更のロケというのが、アパートの一室から、二階建ての一軒やとなった。僕の友達で誰もそんな家に住んではなかったので、途方にくれた。しかし、キャスティングのマリさんがここで大活躍をしてくれた。マリさんの知人の方に一軒家を貸していただけることになったのだ。地味にこのロケーション探しがかなりきつかった。見つけられないと、撮影は出来ない。実は、これのお蔭で何度か胃が痛くなった。 時間がなく、警察に撮影許可の届けを出せなかった。というより、僕がもっと早く見つけられればよかったのだが。場所は、スピンシーンを撮ることが可能な場所。ということで、監督、マリさんと共にロケハンをし、トーランス空港横の駐車場でゲリラ撮影をすることになった。このシーンの撮影予定日は金曜日。その為、その前の金曜日の撮影予定時間と同じ時刻に、確認のため車を走らせた。日没の時間とパーキングに車は残っているのか、警察は来なさそうかを確認したかったのだ。そして、結果はOK。撮影出来るとこの時は判断したのだが、後々トラブルを招いてしまった。 撮影の数日前、機材への保険の支払いと契約にNorth Hollywoodまで行ってきた。レンタル会社の人から紹介してもらったとこだ。保険代はなんと、1300ドル。さすがに保険代は頼んでもまけてくれなかった。そして、撮影前日、監督のヒデさんと、音楽のマサさんと僕とで、機材の調達に向かった。車輌代を浮かせる為に、運転手として音楽家であるマサさんにまで手伝ってもらった。感謝です。車はなんとエルカミーノだった。かなりの年季の入った車にかなりの不安であった。 行き先は、全部で4つ。Valleyの方に一つ、North Hollywoodに二つ、もう一つはソーテルだった。いきなり、エンストの連続という出だしではあったが、何とか順調に進んだ。しかし、3つ目の、Birns&Sawyersというレンタル会社に着いたとき、事態は急変した。機材の重さに車が耐えられなくなったのだ結局、Uホールを借りて、ひとまず解決したのだった。この会社は知っている人はかなり多いと思うが、かなりオススメだ。監督がその場のノリでいくつか機材を足したため、予定より費用が上がってしまったのだ。しかし、いくらなら出せる?と聞かれ、思わずヒデさんが当初より100ドルアップの値段を言った。そうしたら、笑顔でOKと言われた。あれだけ、機材を足して平然と100ドルのみのUPで挑む監督に、それに応じてしまった変な会社。エンタメ業界はまさに気合とハッタリの世界であった。 この日の夜はスタッフ全員を呼んでの、顔合わせを兼ねた、決起集会であった。僕達3人は、少し遅れながらも無地到着した。トモがこちらの準備は進めていてくれたので、予定通り、開始できた。集まった人数はざっと30人。日々香というTorranceの台湾家庭料理屋でやったのだが、入りきらなかった...脚本が完全に出来上がったのは、この日であった。しかも、ロケ先もまだ全て見つかっていなかった。かなりの不安を抱えての撮影スタートとなったのだ。 September 18, 2002
このままだと、5日後の撮影が出来ない。相当焦った。 とにかく、代わりを見つけるため、ダウンタウン周辺を探し回ったが、期待できる結果は得られなかった。ビジネスアワーが終わり、本日のロケハンは止めることにした。まー、何とかなるかと思い、現場に向かった。 撮影は始めての体験。 待ちに待った撮影をやっと体験出来ると、ロケ地を探せなかったことをさっくり忘れ、完全に撮影モードに変わっていた。
息がつまりそうなほど緊迫した空気。 突き刺すような全員の視線が役者に注がれていた。 すでに撮影は8時間を越えていたが、誰一人疲れを見せず、活き活きと動いていた。
しかし、数分後、その行き詰る空気に、ホントに苦しくなってしまった。何がいけないのかよく分からないようなシーンで永遠とテイクを重ねていた。これが監督のこだわりなのねと、妙な納得感を得て、わずか数十分で現場を後にした。 「どうやら、現場は楽しくないらしい。」 初めての撮影でそう思ってしまった。 と、和んでいると、ラインプロデューサーであるユミさんが忙しそうに走り回っていた。どうやら、撮影が予定より全然進んでないらしい。この日のクルーはざっと25人ほど。そのほとんどが映画撮影初参加であったため、撮影の遅れはしょうがないように思えた。明日になれば、明後日になれば自然と撮影スピードはあがるだろうと翌日からの撮影に期待した。 September 19, 2002
住宅街の一通りで、行なったこの撮影はかなりの大掛かりになってしまった。 U-Haulという引越し用のトラックにジブアームという小型クレーンをのせ、走らせながら正面からのショットを撮った。ポストはこちらで用意していたと言っても、バットで叩くとかなり大きな音がした。その音にビックリした近所の人が現れ始めた。 ここで彼らに通報されては、撮影が振り出しにもどってしまう。ということで、住民が出てきたところで、走って説明に行った。許可は取っている、学生映画、直ぐ終わる、迷惑は掛けない等、今考えると全部嘘だったじゃないかというようなことを並べていた。幸い、アメリカでは映画撮影はとても日常的なことであり、人々もとても協力的である。説明に向かうと皆、何ていう映画?いつ見られるの?など協力的な態度だ。 しかし、中には止めてくれ、警察を呼ぶぞといわれることもあった。 そんなときには、前々から準備していたスターバックス券を添えて、お願いをしたこともあった。そんな買収作戦も駆使し、何とかこの撮影を終えることが出来た。 この時すでに映画撮影への興味はすっかり無くなっていた。 結局、翌日からは僕が撮影現場に居ることは無くなった。ロケハンに行っているか、待合室で翌日のスケジュールや予算の打ち合わせをしていた。現場に行くときは、なんらかの問題が起きた時だけになった。 撮影3日目に、撮影に使っていた車のキーがなくなるというハプニングがあった。 車が使えないと撮影は全く行なうことが出来ないという状況だった。皆で探しても見つからない。とりあえず、食事休憩にして鍵屋を呼んだ。1時間半と60ドルのロスであった。
撮影5日目 ロケがまだ確実ではない。悩んだあげく、Goサインを出した。許可がまだ取れてないため、大規模な撮影は行いたくなく、少数で行なうことにした。
僕が行かないと、具体的な撮影場所も分からない、許可だって取ってないということで、クルーや役者には非常に迷惑を掛けてしまった。2時間の遅刻で到着後、直ぐオフィスに向かった。幸い、マネージャーはいたため、交渉を開始した。しかし、無理だと早速言われた。無理を承知で頼んでいるのだから、そんな言葉で引き下がるわけにはいかなかった。 皆には、もう許可は取れていると嘘を言って、準備を始めてもらっていた。 もう撮るしかなかった。とにかく必死で交渉した。どうしようもない状況に立たされた為、頭には血が上っていたが、言葉はどんどん出てきた。嘘がばれないように、事実に少しだけ嘘を交えて脚色していく。どうやら同情してくれたらしく、特別6時間というリミット付きで許可してくれた。 僕の遅刻で迷惑を掛けてしまった皆さん。 ほんとにスイマセンでした。 02闇の旋律 初めてのプロデューサー戦記6 撮影編
何故夜撮かと言うと、監督がこの作品では、白を基調にして撮りたいと言っていたからだ。部屋全体を白く、冷たい雰囲気を出すのであれば、外光が一切入らない夜に、HMIという白い強力な光を放つライトをベランダから当てるのがいいということだった。 しかし、夜撮影はリスクが多い。アパートの一室で行なうため、近所の住民へのケアを考えなくてはいけない。終了が朝のため、クルーが事故を起こさないか。心配は尽きなかったが、それが監督のこだわりであり、そうすることで面白い作品が撮れるのであれば、やらないわけにはいかない。 前述通り、時間が無かったため、監督は撮影の日初めてアパートの一室を見た。実際の窓の大きさ、部屋の間取りなど自分のイメージと多少異なったようだった。そのため、最初に現場に入ったときは、無言でイメージを高めていた。伊藤監督のスタイルに、その場にあるものや雰囲気を瞬時に捉え、もっとも良い演出、アングルを考え出すというのがある。イメージのセットやロケを用意してもらうだけでなく、用意された素材の一番良い部分を引き出す。これは自主制作というほぼ無予算の中で映画製作をし続けた中で得たものだろう。その能力のお陰で、このピンチは乗り切ることが出来た。いや、乗り切るどころか、3本の中で一番の秀作と呼ばれるものが誕生した。 こうして3本11日間の撮影は幕を閉じた。 September 21, 2002
撮影後3日間は死んだように寝て、起きたら何か食べて、また寝た。だが、その時すでにポストプロダクション(編集、音響、音楽など)は始まっていた。 スポンサーがいるため、当然納期はあった。それも、撮影後から1ヶ月なかった。撮影が終わったのが、6月11日。そして、3本中1本は7月1日までに納品しなくてはいけなかった。20日もない内に編集を終え、音響と音楽をつけ、完全なる状態にしなくてはいけなかった。撮影が終わり、一安心したものの一番大変だったのは、実はこのポスプロだった。 最初に仕上げるのは、「BOX」という怖さでは一番定評のある作品だった。一番の見せ場であるお化けが登場してくるシーンの脚本は存在していなかった。現場で監督がインスピレーションに任せて撮ったといっても過言でない。その点、撮影時は苦労も多かったが、それが監督のスタイルであり、良かったとは思う。しかし、編集となると話は別だった。脚本は設計図であり、撮影した映像は素材であり、
編集が終わると、今度は音楽と音響だ。この音がいかに映画に必要不可欠かとてもよく分かった。映像だけの編集が終り、それを見たとき、「あれっ?」と首をかしげてしまった。これでいいの?ととても不安になってしまった。驚くところが分かりにくく、感情も移入しにくく、どうもしっくりこなかった。監督、編集のアツコさん達は全く気にしていなかった事にも、驚いた。だが、音がつくと全く違う物のように生まれ変わった。 音楽は見ている人の感情を高め、驚くところではその効果を何倍にも高める。先ほど書いた、驚くところが分かりにくいというのも音楽が付くことで全く解消された。スピルバーグ監督のジョーズでの曲はあまりに有名だ。あの♪ジャージャン
お化けが這いずってくる音、血を垂らす音によって、迫力が出るかどうかはかかっている。映像編集を見たときに思った、しっくりこなかったというのは、このリアル感が無かったためだろう。音響は、現場で録る音もあるが、大半はフォーリーと呼ばれる作業で作られることが多い。例えば、血のついた手でフロントガラスを這い上がってくるお化けの音であれば、ひき肉を手でグチャグチャこねて、その音を使うなど。また、足音などであれば、スタジオで足踏みをして録ったりする。 September 22, 2002
また、音響担当のダイスケ君はこれが始めての映画製作への参加だった。本職は、音楽のレコーディングなどエンジニアリング、プロデュースなどだ。しかし、初めてとは思えないほどの仕事ぶりであった。現実にありえないような効果音を作るのは、創造性が必要なことである。お化けが這ってくる音がまさかひき肉をこねていた音だとは誰も気づかないだろう。 そして、もちろん監督はこれの全てに立会い、自分でも編集を行なった。だが、まずは自分でやらない。というのも、自分で監督した映像を自分で繋げると、どうしてもこだわりであったり、固定観念にとらわれてしまうとのことだ。エディターは、最初の観客である。脚本にも撮影にもタッチしてないため、客観的に見て、映像を繋げることが出来る。エディターによって一度ぶち壊した映像たちを、また監督が新たな視線でつなげていく。もともと、伊藤監督に変なこだわり等はないが。いい言い方では、監督でありながら、見る側の視点で映画を作っているということだろう。 この編集作業と同時に、プロデューサーであるトモは、本作ホームページのオープニングフラッシュ、特典の壁紙のデザインをしていた。もともと、トモはプロダクションデザイナー(美術)であり、デザインが本職である。 僕達のポストプロダクションでの、一番の苦労は、ADRであっただろう。日本では、アフレコと呼ばれる作業だ。会話は現場で録ることが基本ではあるが、今回では全滅に近かった。この録音はとにかく難しい。映画撮影の中では、一番の技術職であると思う。人間が耳で聞こえないような音も、マイクを通すことで録音されてしまい、ノイズになることはよくあることだ。これを学生が担当したのだから、元より厳しいものではあっただろう。そのため、後からスタジオでセリフをもう一度録音しなくてはいけなかった。だが当然、後録となると口の動きとセリフが異なってくる。何度もやり直しを繰り返したがなかなか上手くいかないものだ。しかも、僕達は日本語の吹き替え版まで作ってしまったため、手間は倍以上かかってしまった。この製作での一番の反省点は、この録音だったと思う。次回作では、これには是非とも気をつけなくてはならない。音声が良くないと、どうしてもチープに見えてしまう。次回への課題だ。 とにもかくにも、こうして無事納期を守り、納品することが出来た。このポストプロダクションにおける、プロデューサーの仕事は分かりにくいと思う。ポスプロのスケジューリングであったり、予算の振り分け、またまた起こりうるトラブルへの対処といったところだろう。時には、夕食を作ったり、徹夜につきあったりと皆のモチベーションを下げさせないようにすることも大事な事であると思う。
さてさて、幸いにもこの作品はスポンサーZAQのHP上で公開され、好評を得ることが出来た。結局は見てくれた人が良かったと言ってくれることが大きな喜びであり、モチベーションである。辛かった制作もこれでこそやったかいがあった。映画を作った以上、より多くの人に見てもらいたいと思うのは、プロであれ、学生であれ、映画を作る者達であれば誰しも共通して言えることだろう。
先ほども述べたように、資金を回収してプロデューサーはやっと終わりだ。なので、僕はまだ終わっていないのだ... 今なお、映画際に出品し続けている。そろそろ各映画祭の結果が出始めるころだ。映画際でグランプリに選ばれれば、そこから様々なチャンスは生まれるだろう。そして、僕の仕事はいつ終わるのだろうか・・・
|
![]()